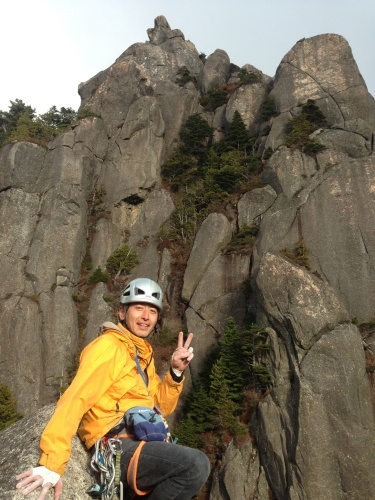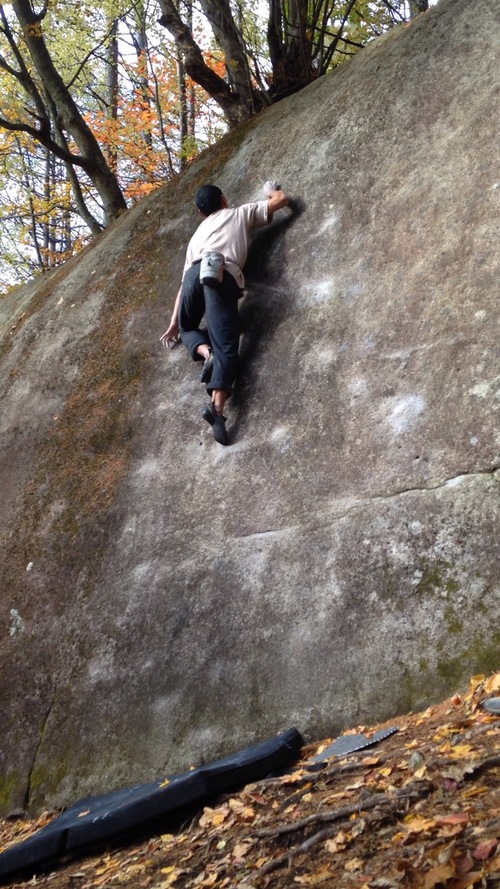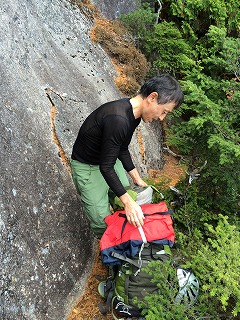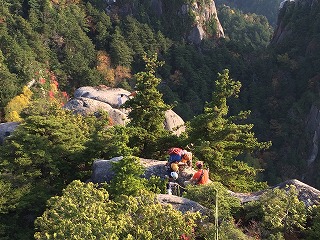瑞牆山十一面でマルチルートの継続登攀をしてきました。
日程:10月11日
メンバー:竹内・熊谷
ルート:十一面奥壁「一粒の麦」→左岩壁「錦秋カナトコルート」
「一粒の麦」
正面壁基部より白熊のコルからの下降路のルンゼ側へ向かうと、白テープやケルンが有るので、
それをたどって10分ほど岩壁基部を回りこんで行くとフィックスロープがあり、その手前の左側のバンドを行くと、取付きに出る。
取付きにて登攀準備
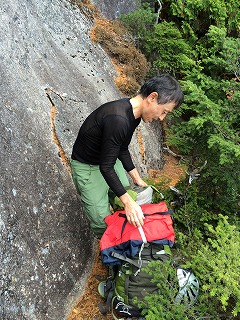
1P目

正面のフェースから3mほどのクラックを登り、スラブを左下へクライムダウンしてテラスヘ。
2P目

右側がフレーク状になったクラックが30mくらい続く、とても気持ち良いピッチ。
ハンドから始まって、だんだん広くなり最後はワイドになる(ワイド部分は5.9くらい)
キャメ#1~#5 (#3は3個あると良い、#5は1個)
3P目

写真のクラックを登り、上部が良く見えるテラスからチムニー内を下降して、ガリー基部でビレイ。
4P目(写真なし)
ガリーを登り、右側にクラックがたくさん有る5P目取付きまで。
5P目(写真なし)
クラックからフェース、ダブルクラックから5.8くらいのオフィズス、ガリーを右へ渡って6P目取付きの木でビレイ
6P目

出だしのカンテから右のクラックへ移るまでが難しい。
上部のクラックは素晴らしく、そのまま奥壁のピークへ出る。
奥壁頂上にて


不動沢側へ数メートル、クライムダウンしてトンネルを通って取付きへ歩いて下降。
10分~15分で着いてしまう。
荷物をまとめて正面壁基部へ移動。
「錦秋カナトコルート」には先行パーティーがおり、取付きで30分ほど待つ。
先行パーティーのセカンドが登り始めたのでスタートするが、1P目終了点手前のレッジでも30分くらい待たされる。
その後のテラスごとに待ち時間があったが、楽しくクライミング出来た。
上部は「100岩場」ではなく「マルチピッチルート図集」を参照されたい。
(2P目の5.10a は辛いと思う)
カナトコ岩の上より下降点を見下ろす
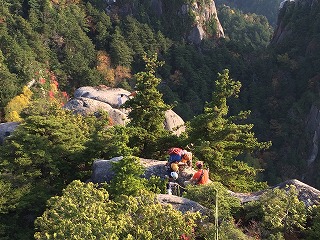
山族黄昏の下降点が混んでいるので、錦秋カナトコルートを懸垂下降した。
充実した一日を終えて

初めての瑞牆での継続でしたが、とても楽しめました。
初動時間をもう少し早くすれば、一日3本も可能では?と感じました。
(技術・体力をもっと向上させたいと思います。)
一粒の麦:1・3・6P 竹内リード
2・4・5P 熊谷リード
錦秋カナトコ:2・4 竹内リード
1・3・5・6P 熊谷リード
参考時間
7:00 植樹祭駐車場
8:20 一粒の麦、取付き
8:50 登攀開始
12:00 一粒の麦、終了
13:00 錦秋カナトコルート、取付き
13:30 登攀開始
16:00 錦秋カナトコルート、終了
17:00 下降終了、取付き
18:00 植樹祭駐車場
記 熊谷